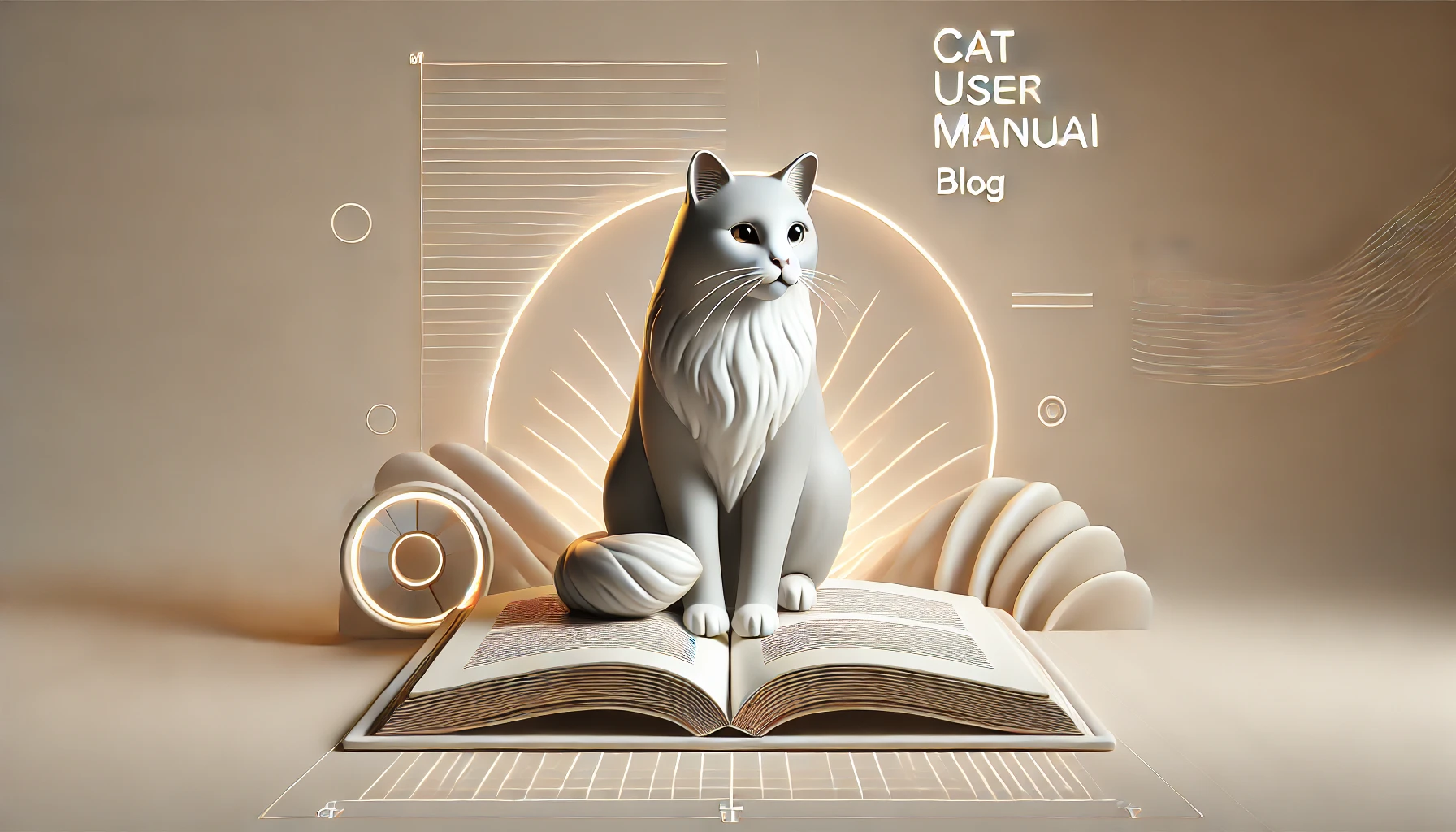私たち猫を「しつけ」たいと思っている人間がいるとしたら、それはまったくもって無理なことなので最初に言っておきます。
私たち猫を「しつけ」たいと思っている人間がいるとしたら、それはまったくもって無理なことなので最初に言っておきます。
私たち猫にはそもそも「しつけ」という概念がないんです(笑)
しかも「しつけ」と言われると腑に落ちないので今回は「私たち猫の取り扱い」という観点で学習していきます(笑)
私たち猫の取り扱いは、犬のそれとは根本的に違いがあります。
犬は群れ生活者で、飼い主さんをリーダーだと思って飼い主さんの喜ぶことをしたがります。それゆえに「叱られる」ことは嫌で「褒められる」ことをしたいと考えます。これは、上手に褒めることでしつけをすることが可能になるわけです。
ところが私たち猫は単独生活者で、他に合わせるという感覚はありませんし、褒められたいという感覚もありません。
たとえ叱られたとしても、それは「怖い」だけで、その人のそばに近寄ることをしなくなります。
また、たとえ褒められたとしても、また同じことをやって褒めてもらおうとは全くもって思いません。叱るとか褒めるとか、私たち猫には何の意味も持たないのですから。
そもそも私たち猫をしつけるなんて、そんなことを考えるのは人間だけですよね。
でも、少しでも、ほんの少しでも、私たち猫を上手に取り扱える魔法があるとしたら・・・・。
そんな思いの皆さんのために、少しだけ、そのコツを教えて差し上げようと思います。
習慣を作ることから始めよう
私たち猫を上手に取り扱いたい(しつけたい)なら、猫はパターン化する傾向の強い生き物だと認識することです。
一度「これはやらないもの」と思うと、ずっとやらない習慣ができあがり、逆に「やるもの」と思うと、いつでもそれをやる習慣が身につきます。
つまり、猫に「やってほしくない」ことがあるならそれをしない習慣を作り上げることが重要なわけです。
例えば、「やってほしくない」ことをしそうになった瞬間に、大きな声を出して驚かせて止めさせます。これは「叱る」のとは違います。あくまでも、ビックリさせて行動を中止させるということが重要です。
これを何度か繰り返していると、私たち猫は「これをやろうとすると、いつもビックリするから止めよう」と考えるようになり、「これはやらない」という習慣ができるのです。
ただ私たち猫は賢いので、飼い主さんが見ていない時にそれが出来るような状態にあると、「飼い主が見てない時はやってもOK」という習慣ができてしまうので、ずっと猫に張り付いて習慣を作ることができない場合は、それなりに工夫も必要です。
例えば乗ってほしくない場所があるなら、飼い主さんがいない間は猫が乗れないように足つぎになっているものを取り去るとか、何か物を置くなど、猫が乗れない工夫をする必要があります。私たち猫をうまく取り扱いたいなら、私たち猫と知恵比べをするつもりでかかってきてほしいと思います。
さて、私たち猫の取り扱いで、「褒めて理解させる」ことは無駄だと言いました。
では「罰」を与えるというのはどうでしょう?罰というのは、叩く、無視する、閉じ込める、といったところでしょうか。
 そもそも罰を与えるというのは、動物の行動心理の観点から見るととても難しいことです。問題行動と嫌悪刺激を関連付けるには、行動が発生してから1秒以内に罰を与える必要があると言われていて、猫に対してこのタイミングを常に守ることは不可能。
そもそも罰を与えるというのは、動物の行動心理の観点から見るととても難しいことです。問題行動と嫌悪刺激を関連付けるには、行動が発生してから1秒以内に罰を与える必要があると言われていて、猫に対してこのタイミングを常に守ることは不可能。
さらに、問題行動に対する罰は与えたり与えなかったりといった一貫性のないものは、まったく無意味です。
体罰にいたっては、人間が力いっぱい猫を叩けば容易に捻挫や骨折を起こしうるし、飼い主さんに叩かれたことのある猫は、「人の手」という刺激に感覚が鋭敏化して他の人の手を見ると引っかいたりすることがあります。また、力づくで押さえつけたりすると、反撃を誘発してしまう場合があります。
このように、私たち猫に罰を与えるという考え自体ナンセンスなのです。
そこで登場するのが、先ほども言った「驚かす」ということなのです。
猫を「はっ!」と驚かせて取り組み中の行動を中断させるわけですが、私たち猫は、急な刺激に対して恐怖心を抱くため、刺激に対して恐怖心を抱くため、驚くことが罰と同じ役目になるわけです。
驚かす行為として有名なのが「猫だまし」でしょうか。手をパンとならすアレですね。
ちなみに私の飼い主さんは、私にやってほしくない行動を私がしようとする瞬間に「ピシッ!」っとつぶやきます。
しかも、「ピシッ!」って言ったのは自分じゃないよという素知らぬ顔をするという小賢しい演技までします。横目で見てるくせに(笑)。
私たち猫の取り扱い方の最後にひとつ。
「猫に芸を仕込む」ことはあきらめてください。ちょっと不本意な言い方をすれば、私たち猫は人間にとって不適切な行動のレパートリーを減らすことで、人間と暮らしていける動物かも知れません。
猫に新しいことを教え込むより、行動をやめさせることを考える方が実用的なのです。
そうは言っても芸を覚える猫もごく一部いるようですから,、挑戦する人は止めませんが飼い主さんにはなってほしくないですね。
▶猫の取扱説明書 ②へ続く
※イラスト/しげるさん(イラストAC)